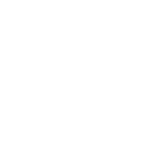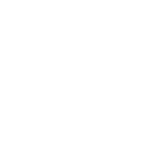2021.03.15
糖尿病発症における膵臓癌の予後
膵がんは早期発見が難しく、偶然の検診や背部痛などの症状から施行されたCT検査によって膵がんが疑われた場合は、確定診断として、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)やEUS-FNA(超音波内視鏡による穿刺吸引診断)が行われる。
しかし、診断時にはすでに肝臓などに転移していることが多く、外科的手術適応は20%程度であり、5年生存率が10%程度という難治がんである。
そのため、さまざまな早期診断に有用なバイオマーカーやスクリーニングのための画像検査の確立が開発されている。
今回、糖尿病の新規発症や増悪を契機に無症状の段階で発見された膵がんでは、比較的早期の膵がんや手術可能な症例が多く、症状により診断された膵がんに比べて生存期間も2倍以上長いことが明らかにされた。
膵がん 489 例について、その診断契機と臨床での特徴や治療後経過との関連を解析した。
489 例のうち、318 例は腹痛や黄疸などの症状を契機に、118 例は無症状時に検診や他疾患の検査を契機に、53 例は無症状時に糖尿病の新規発症や血糖コントロールの悪化を契機に膵がんと診断された。
症状を契機に診断された膵がんでは、ステージ 0 やステージ 1といった比較的早期の膵がんは 8%に過ぎず、手術可能な症例が27%であったのに対し、糖尿病を契機に診断された膵がんでは 40%が比較的早期の膵がんであり、60%の症例が手術可能であった。
検診や他疾患の検査で偶然発見された膵がんにおいては 35%の症例が比較的早期の膵がんであり、68%の症例が手術可能であった。
また、症状を契機に診断された膵がんでは生存期間の中央値が 343 日(11か月)であったのに対し、糖尿病を契機に発見された膵がんでは 771 日(26 か月)と 2 倍以上長く、検診や他疾患の検査中に診断された膵がんでの 869 日(29か月)とほぼ同等であった。
今後、糖尿病を契機に無症状の段階で早期に発見することで、膵がんの治療成績向上につながることが期待される。
本研究成果は、Tohoku Journal of Experimental Medicine誌(電子版)に掲載された。