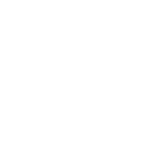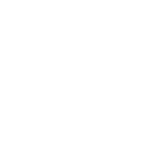2020.06.18
大腸カメラ検査時に発見されるクローン病
クローン病は、口から肛門までの全消化管に潰瘍などの炎症性病変ができる原因不明の疾患である。
日本での罹患者数は約4万人で、10歳代から20歳代に多く見られ、若年層での発症が顕著であり、また欧米先進国での患者数が圧倒的に多いため、高タンパク・高脂肪食である食生活の欧米化が関係しているともいわれる。
本疾患の病変は消化管全域に起こりうるため、その症状は多岐にわたり、断続的にかつ慢性的に寛解と再燃を繰り返す。
口腔から肛門までの全消化管に病変が認められるが、多くは小腸・回盲部・肛門周囲に好発する。
病変部位別「小腸型」、「大腸型」、どちらにも病変のある「小腸・大腸型」に分けられ、小腸・大腸型が多くを占めている。
(症状)
腹痛と下痢が主な症状である。その他に発熱、体重減少、肛門病変(痔瘻・裂肛・肛門潰瘍など)などがある。潰瘍性大腸炎で多く見られる血便・粘血便はそれほど高頻度ではない。
また、結節性紅斑や関節炎など消化管外合併症が出現することもある。
基本的に外科的治療は行わないが、腸閉塞や消化管穿孔を生じてくる場合は、消化管腸切除等の外科的処置を必要とする場合も多い。
(検査)
胃病変や大腸病変の観察・診断には胃・大腸内視鏡検査を用いるが、小腸病変の観察には、従来は小腸造影やダブルバルーン内視鏡検査しかなく、身体への侵襲が大きく診断に苦慮していたが、現在は、消化管開通性をパテンシーカプセルにより評価した後、小腸カプセル内視鏡検査を行う。
小腸用カプセル内視鏡は、以前は原因不明の消化管出血だけが保険適用で、狭窄が疑われるようなクローン病には使用不可であったが、現在適応が拡大され、すでに海外では、小腸疾患全般の診断はもとより、クローン病の粘膜の状態のモニタリングにも利用されている。
また、最近は大腸CT検査が行われることも多い。
(内視鏡所見)
腸の縦軸方向に発生する潰瘍(縦走潰瘍)や腸の粘膜に敷石を敷いたように発生する潰瘍(敷石状病変)が連続性なくスキップして現れるのが特徴である。
炎症が持続するため、狭窄が現れることもあり、潰瘍性大腸炎と異なり、腸管全層に潰瘍は深く浸潤するため、腸と腸または皮膚・膀胱・膣などとの間に瘻孔を形成することがある。
(診断)
① クローン病特有の縦走潰瘍
② 組織検査による非乾酪性の類上皮細胞肉芽腫
③ 腹痛・下痢・全身倦怠感
(治療)
栄養療法により、腸管を安静におくことで寛解状態に導入し、炎症が抑制されて症状の改善がみられる。
一般的には、低脂肪・低残渣の食事が推奨される。しかし近年では狭窄のない場合に限っては繊維質の制限を行わないこともある。
寛解維持にはメサラジンやサラゾスルファピリジンを用い、生物学的製剤(分子標的治療薬)を使った場合にはこれらが寛解維持に用いられる。
手術率は発症後5年で33.3%、10年で70.8%と高く、さらに手術後の再手術率も5年で28%と高率であることから、再燃・再発予防が重要である。
診断後10年の累積生存率は96.9%である。