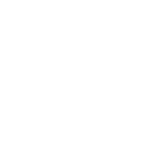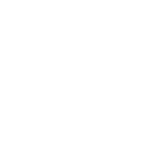2020.10.29
内視鏡検査時の多光子励起顕微鏡診断
内視鏡検査時における消化器・呼吸器・子宮などにおける病変は肉眼的観察によりある程度の診断が可能だが、悪性の最終確定診断には、病変部位から組織片を生検や切除した組織をガラス標本作製し、病理医が顕微鏡で観察・診断する病理診断が不可欠である。
しかし、この方法は、採取する組織片の量によって、診断の精度が左右され、採取量が少ないと診断が確定できない場合があり、また採取量を多くすると生体に対する侵襲が大きくなる。
特に、子宮頸癌の場合、妊娠中の子宮頸部組織の採取はリスクが高いと考えられている。
さらに従来の病理診断では、採取した組織片からガラス標本を作製するまでに、ホルマリン固定や染色など多くの処理工程が必要となり、診断までにかなりの時間を要することも課題である。
最新の生体可視化ツールである多光子励起顕微鏡は、近赤外線により生じる組織深部の蛍光を検知し、組織を傷害せず、深い部位まで可視化できる技術である。
今回、超短パルスレーザーを用いて近赤外線を組織に当て、非線形光学現象による蛍光シグナルを利用して可視化する技術を応用し、組織の切り取りや、ホルマリン固定や染色などの処理を一切行わずに、生きた状態の子宮頸部組織を3次元で観察できる方法が開発された。
これにより、組織を切り取ったり染色試薬を用いたりしなくても、「細胞の核」と「細胞周囲の線維」を詳細に描出することができ、従来の病理診断と比べて、低侵襲で、かつリアルタイムに組織画像を得られる。
さらに、この画像をAIで解析することで、子宮頸部の正常組織、上皮内癌、浸潤癌の画像の定量的分類が可能となる。
これにより、従来の組織診断方法よりも低侵襲・迅速・定量的な癌組織診断の実現が期待される。
また、デジタル画像データが迅速に入手できるため、AIを介した診断にも適しており、さらには、海外でも、発展途上国など病理医を含む医療専門職が少ない地域にもIoTを介した組織診断の提供が可能となり、全世界の人々を対象に、癌診断を展開できると考えられる。
本研究成果は、米国癌学会雑誌「Cancer Research」のオンライン版にに公開された。