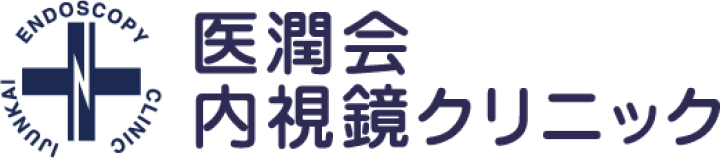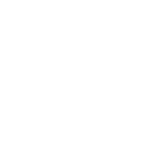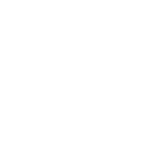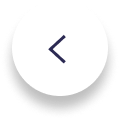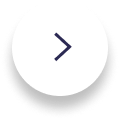2025.10.29
『制御性T細胞』と消化器の病気の関連
免疫には、ウイルスや細菌を攻撃する「アクセル」と、過剰な反応を抑える「ブレーキ」があります。そのブレーキ役を担うのが、2025年のノーベル賞の対象となった制御性T細胞です。この制御性T細胞の働きが弱まると、体が自分自身の組織を攻撃してしまう「自己免疫反応」が起こります。消化器の病気の中にも、この仕組みと深く関係するものがあります。
●自己免疫性胃炎
本来守るべき胃の粘膜を、免疫が誤って攻撃してしまう病気です。
制御性T細胞の働きが低下し、免疫のブレーキが効かなくなることで、胃酸を分泌する壁細胞が破壊されます。その結果、胃酸を出すためのプロトンポンプや、ビタミンB12吸収に必要な内因子も失われ、胃酸分泌の低下やビタミンB12欠乏による貧血を引き起こします。進行すると、萎縮性胃炎が進み胃がんの発生リスクが高まるため、定期的な胃カメラ検査が大切です。
●炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)
腸の免疫が過剰に反応し、粘膜に慢性的な炎症が続く病気です。
近年の研究で、腸内で制御性T細胞の数や働きが低下していることが分かってきました。その結果、炎症を抑えるブレーキが効かなくなり、腹痛・下痢・血便などの症状が繰り返されます。近年は、制御性T細胞の機能異常や腸内細菌との関係が注目され、免疫バランスを整える新しい治療法の研究が進んでいます。
制御性T細胞の研究は、これらの病気の根本的な治療法につながる可能性を持ち、今後の消化器医療の進歩に大きく貢献すると考えられています。