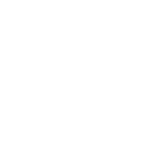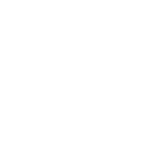2020.12.05
大腸カメラ検査時に発見される潰瘍性大腸炎におけるCD8T細胞の役割
炎症性腸疾患のひとつである潰瘍性大腸炎は、激しい下痢や血便、強い腹痛や発熱などを主な症状とし、増悪と寛解を繰り返す自己免疫疾患である。
本邦での患者数は、20万人以上であり、米国に次いで世界で2番目に多い状況となっている。
新規の免疫抑制剤や生物学的製剤により、病状が好転する寛解状態にいたる率は飛躍的に向上しているが、小児や高齢発症患者には使用が難しい。
さらに長期間の治療により、免疫抑制で懸念される感染症等の副作用や、医療費の高額化などの問題が発生するため、疾患メカニズムのさらなる解明と根本的な治療法の開発が求められている。
潰瘍性大腸炎では、大腸粘膜層に存在する免疫CD4 T細胞の異常とともに、免疫CD8 T細胞による組織障害の関与が考えられている。
今回、潰瘍性大腸炎の病態メカニズムを明らかにするために目的で、大腸粘膜炎症部位に集積するCD8 T細胞の性状解析と遺伝子の発現解析を行われた。
内視鏡検査を受けた潰瘍性大腸炎患者および健常者の大腸生検組織細胞を抽出し、細胞を分離するセルソーターを用いてCD8 T細胞を分取した後、シングルセルRNAシーケンスによりCD8 T細胞の遺伝子発現パターンを1細胞レベルで解析した。
腸管は食物由来の雑多な外来抗原やアレルギー起因物質、病原性微生物などに常に曝されている場所であり、全身の免疫系とは異なる特殊な免疫細胞によって独自の生体防御システムを備えているが、この解析により、大腸に局在するCD8 T細胞が14もの非常に多様な細胞集団を形成していることが明らかにされた。
さらに、健常者に比べ、潰瘍性大腸炎では大腸に常在するメモリーCD8 T細胞の割合が著しく減少しており、IL-26を産生するCD8 T細胞と活性化した細胞傷害性CD8 T細胞の割合が大きく増加していることが発見された。
IL-26は免疫細胞が産生する炎症関連因子の一つで、これまでに主にCD4 T細胞によって産生されることが報告されていたが、大腸にはIL-26を産生するCD8 T細胞が存在し、潰瘍性大腸炎ではその細胞集団が著しく増加していることが明らかになった。
これらより、炎症関連因子IL-26が大腸ではCD8 T細胞によっても産生されていることが初めて明らかとなり、潰瘍性大腸炎の炎症にIL-26が関与している可能性が示唆された。
IL-26を標的とした難治性の自己免疫疾患・慢性炎症疾患に対する新たな治療法の臨床応用が期待できる。
本研究結果は英国Nature Publishing Group発行の学術誌「Nature Medicine」オンライン版で公開された。