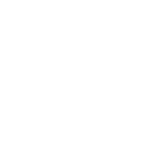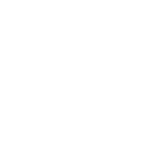2022.08.30
胃・大腸内視鏡検査時の生検における内視鏡医と病理医の連携
胃・大腸内視鏡検査時に良性・悪性腫瘍に遭遇することが多いが、ほとんどは肉眼的観察で判断可能な場合が多い。
しかしながら、確定診断は病理診断となる場合が多く、生検時の検体を適正に保存提出することが重要である。
まず、臨床医の関心領域(病変部または非病変部)から採取されていることが第一の要件である。
生検病理診断には関心領域の質的情報が常に求められている。
この「質的情報」とは腫瘍や非腫瘍(炎症、感染、異所症、化生、再生、循環障害、沈着症など)といった病理学総論における病変区分のことを言う。
通常、腫瘍の病理診断では良·悪性の判断がその開始点となる。
良・悪性の判断材料は細胞異型と構造異型が基本であるため、挫滅のほとんどない良質な生検組織が適している。
また、生検組織内に非腫瘍部組織が含まれていることが望ましい。
非腫瘍部組織からの逸脱具合ならびに非腫瘍部構成細胞との類似性の評価が病理診断に必須であるため、特に異型度が極めて低い分化型胃癌(いわゆる超高分化な胃癌)の生検診断では重要である。
採取組織の人工的な挫滅、乾燥、自家融解、腐敗が病理診断を大いに妨げることは明白であるため、検体の採取と取り扱いには細心の注意を払う必要がある。
それを実践するためには、生検組織がどのような状態(挫滅の有無·程度、生検深度など)になっているかを、できれば内視鏡施行医が自ら検鏡して確認することが望ましい。
また、生検組織の量と個数が論じられることがあるが、粘膜筋板を含む十分な量の組織が採取されていれば生検個数は大した問題ではない。
むしろ病変の主座(粘膜内、粘膜下組織、それ以深)を把握したうえで生検に臨むことが肝要である。
例えば、比較的小さなGIST (gastrointestinal stromal tumor)をはじめ、glomus tumorや神経鞘腫など固有筋層内に主座を置くことが多く、腫瘍は粘膜生検をいくら繰り返しても診断確定に至らない。
通常、鉗子生検で得られるのは粘膜層および粘膜下組織浅層付近の病理組織学的情報であることを再認識し、病理医に対して、内視鏡検査における生検時のデータを詳細に報告するべきである。