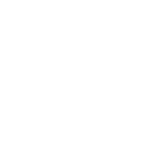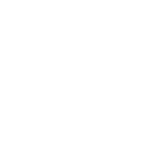2022.08.23
胃カメラ・大腸カメラ検査における胃・大腸内視鏡医と臨床医の連携
胃・大腸内視鏡検査時に良性・悪性腫瘍に遭遇することが多いが、ほとんどは肉眼的観察で判断可能な場合が多い。
しかしながら、境界領域病変や稀な特殊病変における病理診断の役割は重要であり、臨床医と病理医との連携は非常に大事になる。
日常の臨床医が前向きに診断する際には、臨床画像から病変の構造、組織構築を類推し診断する場合、異常を判断する方法として、周囲の正常と思われる部分との表面性状の比較や境界の有無、内視鏡画像であれば色調変化などを参考とする。
内視鏡画像では、色調を捉えることができるという利点があり、さらに生検手技の確立、色素内視鏡、超音波内視鏡(endoscopic ultrasonography; EUS)や拡大内視鏡、特殊光観察や超拡大内視鏡の登場により、診断学はさらなる進化を遂げてきた。
しかし、内視鏡画像は病変の最表面しか見えておらず、病理診断における断面像とは見ている次元が異なる。
EUSは消化管壁の断層を描出し診断するという意味では病理組織断面に近いが、これもEUS所見と病理組織学的所見の切除標本との繰り返す比較より診断精度向上してきている。
病理組織画像を平面的な2次元の断面図から立体的な3次元へ、さらにはX線画像、内視鏡画像、拡大内視鏡画像とも対比可能な最表面の組織標本作製もできることが期待される。
色素内視鏡観察では周囲と凹凸の異なる部位や模様の異なる部位の認識、領域性を視認し、拡大内視鏡観察では表面の状態をより細やかに観察し、周囲と異なる領域を血管形態や表面構造を見ることで認識し、生検部位(内視鏡治療時の切除範囲も含め)の手がかりとしているのが一般的と思われる。