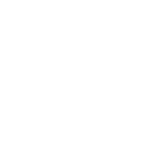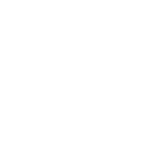2020.11.05
胃カメラ検査時に発見される胃癌に対する抗PD-1抗体治療
胃癌の発生原因のほとんどがピロリ菌によるものであり、内視鏡検査の向上や除菌率の普及により罹患率は減少しているが、依然としては罹患率・死亡率ともに上位にランクされる癌種である。
その治療として、早期癌の場合にはEMRやESDなどの内視鏡的切除が行われるが、進行癌においては手術や化学療法が行われている。
また、転移を伴う難治性胃癌に対しては、近年、抗PD-1抗体などの免疫チェックポイント阻害剤などによる免疫治療が効果を上げているが、胃癌症例の多くは抗PD-1抗体治療に抵抗性を示すことが報告されている。
今回、胃癌組織内の免疫状態の詳細な検討により、胃癌組織中に抗腫瘍免疫を抑える働きがある制御性T細胞が多く存在する一群が存在することが明らかになった。また、網羅的遺伝子解析により、この群には胃癌のドライバー変異として知られるRHOA遺伝子の体細胞変異が多く存在していることも明らかにされた。
RHOA変異陽性癌細胞が産生する遊離脂肪酸は細胞傷害性T細胞より制御性T細胞によって効率的に取り込まれることで、腫瘍内の制御性T細胞の増加に寄与していた。
一方、RHOA変異はPI3K-AKTシグナル伝達経路を活性化することにより、細胞傷害性T細胞を引き寄せるケモカインの生成を低下させ、RHOA変異胃癌は、制御性T細胞が多く集簇し免疫応答が弱い腫瘍環境を形成していた。
これらのデータから、PI3K阻害薬と抗PD-1抗体を併用することで、免疫抑制的な腫瘍環境が改善され、抗腫瘍効果が増強することが明らかになり、新たながん免疫併用療法の可能性が示唆された。
本研究成果は、米国科学雑誌「Immunity」電子版に掲載された。