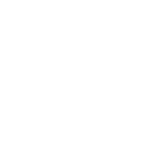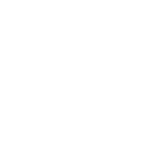2020.10.22
転移リンパ節評価による食道癌治療効果判定
進行性食道癌は、リンパ節への転移を高率で伴うため、抗癌剤治療後に手術を施行することが多く、術前抗癌剤の治療効果が大きい症例は良好な術後の予後が得られることが分かっており、正確な治療効果の判定が重要になる。
術前治療の病理学的な効果判定は、治療前の原発巣腫瘍面積に対する治療後の残存腫瘍面積の割合で評価される。
この評価では残存腫瘍の割合が小さいほどGradeが高く、化学療法の効果が大きかったことが表され、このGrade分類が術後の再発や予後の重要な指標になることが明らかになっている。
しかし、食道癌では原発巣の進展以上にリンパ節転移の程度がより強く予後を反映するため、原発巣より転移リンパ節における治療効果判定の方が正確に予後を反映すると考えられる。
今回、術前に抗癌剤治療後に根治手術を施行したリンパ節転移を伴う胸部食道癌を対象に、抗癌剤治療の治療効果を病理学的に判定した。
主病巣の病理学的治療効果判定として、残存腫瘍の割合別に4段階のGradeで分類し(Grade I:50%>、Grade II:10-50%、Grade III:<10%、Grade IV:0%)、Grade I、II を非奏効群、III、IVを奏効群とした。
また、転移リンパ節の治療効果判定として、転移リンパ節の治療前の腫瘍面積と治療後の残存腫瘍面積を足し合わせることで前述の4段階に分類し評価した。
その結果、転移リンパ節の治療効果判定は奏効群48.0%、非奏効群52.0%と判定され、59.9%の症例で原発巣と転移リンパ節における病理学的治療効果が異なっていた。
予後に関する検討では、転移リンパ節の治療効果判定gradeによって段階的に成績が異なり、また奏効群は非奏効群と比較して生存率が明らかに向上していることが明らかになった。
また、原発巣とリンパ節の病理学的な治療効果による予後曲線を比較すると、転移リンパ節の治療効果判定の方がより顕著に生存率を反映した。
生存期間における多変量解析ではリンパ節の病理学的治療効果判定が独立した予後因子であったが、原発巣の判定は予後因子にはならず、また術後の再発形式に関する検討では、原発巣・リンパ節ともに非奏効群では奏効群と比較してリンパ行性再発や血行性転移臓器再発の頻度がそれぞれ高く、その傾向は原発巣よりもリンパ節における治療効果判定で顕著であった。
これらのことから、転移リンパ節における病理学的な治療効果を判定することは、術前化学療法後に手術を施行した食道癌の術後予後予測や再発予測において優れていることが示唆された。
これにより、個々の食道癌症例に適した術後のオーダーメイド治療が可能となり、食道癌全体の治療成績の向上につながることが期待される。
本研究成果は、米国科学誌「Annals of Surgery」に公開された。